突然、「ウーーーッ」とサイレンが鳴る。続いて聞こえてくるのは「地震です」「火災が発生しました」というアナウンス。揺れてはいないし、火は上がっていないけれど、机の下に潜って、そのあと教室をゆっくりと出て行く……。
皆さんも小中学生の頃に、こんな避難訓練を何度か経験したことがあるのではないでしょうか。訓練とは本来、緊張感を持って取り組むべきですが、「経験のない災害」を想像するのはなかなか難しいものですよね。
どのように襲ってくるのか実態の掴みにくい災害の危なさを、もっとリアルに感じることができたら、訓練にも身が入るし、いざという時により適切な避難行動を取れるはず――そんな思いを胸に、ARやVRを用いた“新しい防災啓蒙の形”を世界に発信している人がいます。神奈川歯科大学教授の板宮朋基さんです。
板宮さんは、「AR災害疑似体験アプリDisaster Scope®」をはじめとしたさまざまな防災コンテンツを、Unityを用いて制作されてきました。なぜ、ゲーム開発プラットフォームであるUnityを採用したのか。そもそもどういった経緯で、災害擬似体験コンテンツをつくろうと思い立ったのか。詳しくお話を伺ってきました。

防災への意識の芽生え、VRとの出会い
──板宮さんは、もともと防災関連の研究やお仕事などをされていたのでしょうか。
板宮:いえ、全然そんなことはなくて。今はこうして防災関連でお声がけいただくことが多いですが、2011年前後までは、医療分野での3DCG活用などが主な領域でした。「レントゲン画像をうまく立体的にモデリングするには?」といったことを研究テーマにしていました。
──「2011年前後までは」というと、きっかけはやはり東日本大震災に?
板宮:はい、そうです。あの震災で多くの人々が犠牲になったのを目の当たりにして、「自分が持っている技術で、何か貢献できることはないか」と考え始めました。そして、翌年の2012年4月に、津波等避難ナビシステム「デジタル皆助ナビ」を発表しました。(※デジタル皆助ナビの画像はこちらを参照)
デジタル皆助ナビは、人々の安全な避難行動を促すためのシステムです。有事の際、スマートフォンなどの身近なデバイスで閲覧できる地図に、災害状況からシミュレートした“危険な方向”を表示させることで、安全なルートでの避難誘導を試みます。
──それが初めてつくった防災コンテンツだったと。この時はまだ、ARやVRの技術は活用されていなかったのですね。
板宮:そうですね。Oculus Rift DK1(Development Kit 1)もまだリリースされていませんでしたから、「個人でVRやARを用いたコンテンツをつくろう」なんて発想自体、容易にできない時代だったと思います。
──そこから、板宮さんがARやVRに触れ始めた経緯について、ぜひ教えてください。
板宮:VRに近づくきっかけは、TwitterでフォローしていたGOROmanさんの投稿でした。2013年の春、彼のツイートで初めてOculus Riftの存在を知って、自分でもすぐに入手しました。
当時はVRコンテンツがそれほど多くありませんでしたが、GOROmanさんらが旅行中の映像をOculus Rift向けにライブ配信した「オキュ旅」などは、今でも印象に残っています。あれを見て、「VRの映像は“視聴するもの”ではなく、“体験するもの”になり得るのだ」と強く実感したんですよね。
──明確にVRコンテンツのつくり手側に回ろうと思い始めたのは、いつ頃からでしたか?

板宮:2014年の春から夏にかけてです。この期間に、3つの契機がありました。
1つ目は、4月に愛知工科大学に赴任して、初めて自分の研究室を立ち上げることになったことです。研究室に学生たちを呼び込むため、何か最近の技術的なトレンドを取り入れてみようかと考え始めていました。
2つ目は、6月に豊橋で行われたVR開発者向けイベント「Oculus Festival」に参加したことです。VRを利用したさまざまなコンテンツが展示されていて、すごく将来性を感じましたし、自分の研究領域でも何か活用できたらいいなと思い始めました。
3つ目は、日本にOculus Rift DK2が届き始めたことです。初代であるDK1に比べると、大幅にスペックやシステムが改善されていて、扱いやすいデバイスに進化していました。
──それらの要素が重なって、自分もVRの開発者になってみようと。
板宮:はい。それで、「どういうソフトでVRコンテンツをつくれるのか?」と調べて行き着いたのが、Unityだったんですよね。利用者も多く、先駆者たちがコミュニティを形成して、さまざまな情報共有をしてくれていて。このソフトなら、わからないことがあってもすぐに解決できそうだなと感じて、安心して使い始められました。
スピーディーな開発、それを支えたUnityの利便性
板宮:そんな経緯を経て、Unityを使用して最初につくったのが「津波ドライビングシミュレーター」です。
津波災害では、車に乗って、あるいは乗ったまま逃げようとして逃げきれず、波に飲まれてしまう人が少なくありません。「津波が起きたら車を降りて避難しよう」という呼びかけは所々でされているものの、乗車したままの逃げ遅れ被害は後を断たないのが現状です。
──たしかに、「車のほうが速く安全に逃げられるのではないか」と考えてしまうのもわかる気がします。
板宮:そうですよね。「なぜ車に乗ったままの避難が危ないのか」ということは、口頭で説明してもなかなか伝わりにくいものです。このシミュレーターは、VRによって擬似的に「運転中に津波被害に襲われる体験」をしてもらって、その危険性を身体で覚えてもらうことを目的としています。
──VRだからこそ、没入感があって、よりリアルに危険を感じられますね。
板宮:これを体験しておくことで、有事の際にも素早く「車を降りる」判断ができるのではないか、と考えています。
──こちらのシミュレーターは、どれくらいの期間で制作されたのですか。
板宮:改良は数え切れないほど重ねていますが、最初のプロトタイプは2週間ほどでつくれました。
──2週間! 初めてのVRコンテンツの制作ながら、かなりスピーディーに仕上がったのですね。
板宮:Unityに汎用性の高いアセットが豊富に用意されていたのが、とてもありがたかったですね。それらを上手く活用することで、限られた時間の中でイメージに近いものを素早く形にすることができました。

日中は本業の研究や講義が詰まっていたので、主に制作は帰宅してから就寝までの時間で取り組みましたが、チュートリアルやライブラリのナビゲーションも充実しており、初心者でもすぐにソフトの勘所をつかめました。
もしUnityのような、つくり手にやさしいソフトを使っていなかったら、忙しさに追われて、使い方を覚えるまでに挫折していたかもしれません。
VRからARへのシフト、その理由
──その後、板宮さんは津波だけでなく、火事、地震などもカバーした「AR災害疑似体験アプリDisaster Scope®」をリリースされましたね。VRからARに移行したのには、何か理由があったのでしょうか。
板宮:試行錯誤を重ねていくうちに、防災体験とARの相性のよさに気づき始めたんです。そのポイントは、大きく2つあります。
1つは、ARだと「自分の今いる場所」が有事の際にどうなるのかを、擬似体験できることです。取材班の皆さんにも先ほど、ARの津波と火事の体験をしていただきましたが、いかがでしたか?


──すごく臨場感がありました。よく災害の報道などで「浸水◯センチ」といった表現が使われますが、あれってどのくらい危ないのか、把握しにくいなと感じていて。けれども、このスコープを通して見ることで、「こんなに危ない状況になるのか」ということがすぐに分かりできますね。火事体験のほうは、煙の出方がとてもリアルで、しゃがんで逃げる必要性などをよく理解できました。
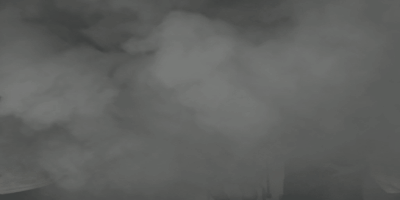
板宮:このように、VRは「つくられた空間内」での体験ですが、ARなら「今いる場所」での体験を提供できます。日常の拠点が有事の際に、どれほど危なくなるのかを体感しておくことで、素早く正しい避難行動を取れる確率は、大きく上がるはずです。
──普段の避難訓練も、Disaster Scopeでどれほど危なくなるのかを知っておくと、より身が入りそうですね。
板宮:もう1つの相性のよいポイントは、汎用性の高さです。VRは投影するものすべてをCGなどで作成する必要があります。リアルな場所に対応したシミュレーションをつくろうとすれば、その都度でかなりの制作時間とコストがかかってしまいます。
一方、ARならば基本となるシステムをしっかりつくりこめば、現地のハザードマップなどを参照しながら適宜調整をすることで、どこでもその場でリアルな災害体験を提供できるんです。
──ARのほうが、よりリアルな被災体験ができる上に、汎用性が高く広めやすいと。
板宮:そうですね。現在は、このDisaster Scopeをさまざまな人、学校、自治体に知ってもらい、活用してもらうための啓蒙活動に注力しています。
次なる防災体験は「触覚」

──今後は、Disaster Scopeをどのように進化させていきたいと考えられていますか。
板宮:視覚と聴覚の体験クオリティはかなり高くなってきたので、今後は触覚体験の再現にもトライしていきたいです。
──浸水や津波の体験も、足元に水の流れを感じられるようになると、さらにリアルな被災体験になりますね。
板宮:これまでの実験では、ファンで風を与えたり砂を用いたりして、水流の表現を試みてきましたが、まだまだ満足のいく質感には至れていません。おそらく、これから触覚に対応したデバイスも出てくるはずなので、積極的に活用していきたいなと考えています。
──Unityはゲーム機やスマートフォンはもちろん、HMDやコントローラーなどの各種デバイスが新しく登場した際は、すぐUnityで利用できるようにサポートすることを積極的に取り組んできました。この点は今後も真剣に取り組んでいくつもりです。
板宮:これまでもそうでしたが、Unityは追加や更新などを含め、連携しているサービスのサポートが迅速で手厚く、開発者としてはとても助かっています。
あと、2018年からUnity Hubが実装されたおかげで、過去のバージョンで制作したプロジェクトの変換や活用がしやすくなったのは、本当にありがたく感じました。今までの蓄積が無駄にならず、それらを資産として運用しやすいように配慮してくれるUnityは、積み重ねがものをいう「研究」の文脈と、とても相性がいいなと思っています。
防災の啓蒙に、終わりはない
──防災関連の取り組みにおける、今後の抱負などがあれば、ぜひ聞かせてください。
板宮:防災や減災にまつわる取り組みは、非常に普遍的で、これから先も必要性がなくなることはありません。いつ来るか分からない災害に対して、ずっと危機意識を持ち続けることは難しい。それは人の心理的な構造上、致し方のないことでもあります。
だからこそ、継続的に注意喚起をしていくことが大切なんです。一度やったら終わりではなく、常に一定の危機感を保てるように、何度でも呼びかけていく。繰り返しの地道な啓蒙が、防災の宿命です。
できることから手探りで始めた防災関連の取り組みでしたが、今では生涯をかけてずっとやっていきたいと感じています。直近の目標としては、Disaster Scopeを用いた被災体験を、全国の小学生全員が一度は経験できるくらいに、広めていきたいですね。

──この記事は、Unityを使っている多くのユーザーの皆さんの目にも触れると思っています。先輩クリエイターとして、つくり手の皆さんに何かメッセージなどをいただけたら嬉しいです。
板宮:そこまでUnityのプロフェッショナルというわけではないので、あまり大きなことは言えませんが……そうですね、つくったものはぜひ、どんどん外に発信していてほしいなと思います。
僕自身、この防災関連のコンテンツの必要性に確信が持てたのは、外に発信したからこそなんです。Twitterで制作物した動画を発信していたら、たまたまバズることがあって。そのバズをきっかけに、国内外のさまざまなメディア、自治体から問い合わせが来るようになったんですよ。
──私たちも、板宮さんの取り組みは、たまたまSNSで発信されているのを見かけて知りました。
板宮:SNSで発信したおかげで、自分の取り組みが社会のニーズとしっかり接続していることを実感できたし、共同で研究や啓蒙に取り組んでくれるパートナーも増えていきました。それらはすべて、公開しなければ生まれなかった気づきや縁でした。
あなたが今つくっているもの、やっていることを、ものすごく必要としている人が、どこかにいるかもしれない。それは、その人たちに情報が届いて、初めて反応が返ってきて分かることです。外に発信することで、見えるもの、繋がるものが、きっとあります。だから皆さんも、もし何かつくれたら、臆せずにどんどん発信していってほしいなと思っています。
防災アプリが持つポテンシャルを実感
今回は「防災の日」にちなんだ、特別インタビューをお届けしました。
私たちUnityのメンバーも板宮さんのお話を伺って、防災アプリが持つ大きなポテンシャルを感じると共に、その技術的な支えにUnityが貢献していたことを、とても誇らしく感じました。
板宮さんいわく、「防災界隈のクリエイターも、啓蒙活動を促すエヴァンジェリスト的存在も、需要に対して全然足りてない」とのこと。もし、こちらの記事を見て「私に何かできるかもしれない、やってみたい」と思われた方がいたら、ぜひ何か小さくつくり始めたり、行動を始めたりしてみてはどうでしょうか。それを、SNSなどで発信してみてください。
ここを起点に、防災の領域で第二の板宮さんのような存在が出てきてくれたら、そして少しでも防災の輪が広がっていってくれたら、それほど嬉しいことは他にありません。
(撮影:栗原論)
